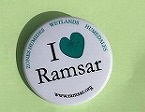NPO The Hinuma Ecosystem Restoration Project
大型水槽への植え付け


 5月例会(2022/05/11)の時に所有しているヤナギモ・エビモ・マツモ・コウガイモ・セキショウモ・クロモ・リュウノヒゲモを植え付け大型用器の水中へ素焼き鉢と共に
設置した。深さが80cmあるので手では底まで届かないのでどの様にするのが一番良いか考え、写真のような物を作りました。30号鉢なので用土を一杯まで入れると
重量が結構あります。一つまだ植え付けていませんがササバモを予定しています。ただ深さ的に大丈夫かな?という心配はあります。
植木鉢の中で定着をした物を本年度は広浦漁港の中へ専用区域を設け設置植え付けを予定しています。この専用区域を設置するための大きさは約2坪です。水深40cmほどの場所へ
木枠を高さ80cmに四角く区切り波除を作ります。専用区を設置するため広浦漁港利用者組合、茨城町農業政策課、水戸土木事務所など関係機関より許可を頂きました。
施設設置原資として本田記念財団より30万円の助成を頂きました。
5月例会(2022/05/11)の時に所有しているヤナギモ・エビモ・マツモ・コウガイモ・セキショウモ・クロモ・リュウノヒゲモを植え付け大型用器の水中へ素焼き鉢と共に
設置した。深さが80cmあるので手では底まで届かないのでどの様にするのが一番良いか考え、写真のような物を作りました。30号鉢なので用土を一杯まで入れると
重量が結構あります。一つまだ植え付けていませんがササバモを予定しています。ただ深さ的に大丈夫かな?という心配はあります。
植木鉢の中で定着をした物を本年度は広浦漁港の中へ専用区域を設け設置植え付けを予定しています。この専用区域を設置するための大きさは約2坪です。水深40cmほどの場所へ
木枠を高さ80cmに四角く区切り波除を作ります。専用区を設置するため広浦漁港利用者組合、茨城町農業政策課、水戸土木事務所など関係機関より許可を頂きました。
施設設置原資として本田記念財団より30万円の助成を頂きました。
関東水と緑のネットワーク助成金獲得

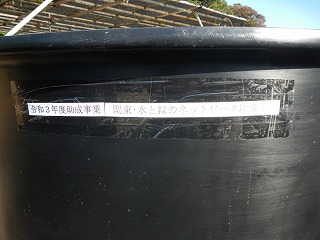
 令和3年度、関東水と緑のネットワーク事業に応募して事業を認められ助成金として50万円をゲットできました。
事業内容はこれまで使用していたプラスチックの容器に比べ何十倍もの水量を入れることの出来る大型水槽購入設置です。
この容器は千葉県立中央博物館で使用している物と同じ物です。約直径1.5m、深さ0.8mのポリエチレン製ですので、柔軟性があり割れることもなく
半永久的に使用できると思っています。食品や鮮魚などに使用されているようです。業者さんの協力もあり少し値引きをしていただきました。
水量が沢山入るということは夏場の急激な水温変化に対応できると思います。
10月末に購入し11月3日の設置を会員皆で行いました。涸沼周辺で採取したヤナギモとエビモを植え付けました。筑波大学より頂いた6種類の植物は
越冬のため葉は枯れてしまいましたので翌年の5月に植え付け予定です。
令和3年度、関東水と緑のネットワーク事業に応募して事業を認められ助成金として50万円をゲットできました。
事業内容はこれまで使用していたプラスチックの容器に比べ何十倍もの水量を入れることの出来る大型水槽購入設置です。
この容器は千葉県立中央博物館で使用している物と同じ物です。約直径1.5m、深さ0.8mのポリエチレン製ですので、柔軟性があり割れることもなく
半永久的に使用できると思っています。食品や鮮魚などに使用されているようです。業者さんの協力もあり少し値引きをしていただきました。
水量が沢山入るということは夏場の急激な水温変化に対応できると思います。
10月末に購入し11月3日の設置を会員皆で行いました。涸沼周辺で採取したヤナギモとエビモを植え付けました。筑波大学より頂いた6種類の植物は
越冬のため葉は枯れてしまいましたので翌年の5月に植え付け予定です。
新しい場所へ実験場の引越し


 令和2年6月10日より旧実験場の解体を始めた。今度の場所は下石崎地区の農業活動組織が民地を借用して県道脇にビオトープを作っている一角を借りる事と成った。
この直ぐ近くが、町で駐車場を整備している涸沼のビューポイントである。数年後には環境省の仮称水鳥湿地センターを建設する予定地である。
場所としてはこれ以上のところは無いと思われる。直ぐ近くの所に住んでいる会員の家よりバックホーを持ってきて整地をした。旧実験場とは目と鼻の先であるが
以前の所は道路からは全然見えない場所であったが、今度の場所は吹きさらしの状態で視界を遮るものは何も無い、盗難に遭うことは予想も出来ない場所である・
軽トラックに何台もポリタンクやタライ、大型バケツなどすべての物を運んできたが、1トン水タンクはトラックに1個積むのがやっとで重いので後日と言う事になり
2個あったのを其処に残してきた。7月8日の例会日にユニック車で行くと大きな水タンクが無くなっていた。誰か知らないかと聞くと誰も知らないという事だ。
大きな1トン水タンク2個を盗まれてしまったのだ。この様な事が2度と発生しないことを祈りながらの新しい実験場整備がスタートしました。
令和2年6月10日より旧実験場の解体を始めた。今度の場所は下石崎地区の農業活動組織が民地を借用して県道脇にビオトープを作っている一角を借りる事と成った。
この直ぐ近くが、町で駐車場を整備している涸沼のビューポイントである。数年後には環境省の仮称水鳥湿地センターを建設する予定地である。
場所としてはこれ以上のところは無いと思われる。直ぐ近くの所に住んでいる会員の家よりバックホーを持ってきて整地をした。旧実験場とは目と鼻の先であるが
以前の所は道路からは全然見えない場所であったが、今度の場所は吹きさらしの状態で視界を遮るものは何も無い、盗難に遭うことは予想も出来ない場所である・
軽トラックに何台もポリタンクやタライ、大型バケツなどすべての物を運んできたが、1トン水タンクはトラックに1個積むのがやっとで重いので後日と言う事になり
2個あったのを其処に残してきた。7月8日の例会日にユニック車で行くと大きな水タンクが無くなっていた。誰か知らないかと聞くと誰も知らないという事だ。
大きな1トン水タンク2個を盗まれてしまったのだ。この様な事が2度と発生しないことを祈りながらの新しい実験場整備がスタートしました。
盗難のため解体、引越し


 令和元年12月21日下石崎産直市場あいあいで手打ちそば食べ懇親会を開催した。筑波大学留学生や茨城町長小林氏に参加を頂き、会員の時田さんが自宅の
畑で栽培したそば粉を原料に手打ち蕎麦を打った。温かい蕎麦はアイ鴨の出汁で食べ、冷たい蕎麦は昆布出汁の特性汁で十分な量を皆食べることが出来た。
清水会長宅で栽培された那珂川河川敷の砂地で作られたねぎの一本焼きに醤油を付けて頬張るとこの冬は風邪を引かないだろうなどと言いながらワイワイガヤガヤ
と時間の過ぎるのも忘れて時間をつぶした。午後3時過ぎに片づけを開始し4時には皆退散した。帰り際に実験場の見回りをして岐路に付いた。
令和2年2月5日NPOの定例会で実験場に集まると地上の容器に涸沼湖の水を汲み上げて実験している施設に異常な状態が発生していた。
水があまり無いので、電源を確認に行くと有る筈の鉛バッテリー4個が無くなっている。切断されている線の様子から判断すると盗まれたようである。
この様な事が起こるとは予想もしない自体であるので、2度3度と盗難に遭うことが予想されるので、場所の移動をする事にした。
令和元年12月21日下石崎産直市場あいあいで手打ちそば食べ懇親会を開催した。筑波大学留学生や茨城町長小林氏に参加を頂き、会員の時田さんが自宅の
畑で栽培したそば粉を原料に手打ち蕎麦を打った。温かい蕎麦はアイ鴨の出汁で食べ、冷たい蕎麦は昆布出汁の特性汁で十分な量を皆食べることが出来た。
清水会長宅で栽培された那珂川河川敷の砂地で作られたねぎの一本焼きに醤油を付けて頬張るとこの冬は風邪を引かないだろうなどと言いながらワイワイガヤガヤ
と時間の過ぎるのも忘れて時間をつぶした。午後3時過ぎに片づけを開始し4時には皆退散した。帰り際に実験場の見回りをして岐路に付いた。
令和2年2月5日NPOの定例会で実験場に集まると地上の容器に涸沼湖の水を汲み上げて実験している施設に異常な状態が発生していた。
水があまり無いので、電源を確認に行くと有る筈の鉛バッテリー4個が無くなっている。切断されている線の様子から判断すると盗まれたようである。
この様な事が起こるとは予想もしない自体であるので、2度3度と盗難に遭うことが予想されるので、場所の移動をする事にした。
水生植物の増殖
 平成30年6月21日、茨城町立葵小学校の体育館脇屋外で4年生55名
の親子学習会にて当NPO会員の指導で沈水植物の株分け増殖授業を行いました。
平成30年6月21日、茨城町立葵小学校の体育館脇屋外で4年生55名
の親子学習会にて当NPO会員の指導で沈水植物の株分け増殖授業を行いました。
最初に児童たち1人2個づつ一升枡程度の大きさの木箱を組み
立てました、 会員がリサイクル木材を活用して組み立てキット状に準備をした部材を分け、釘と金槌で父兄の手伝いの下、何とか組み立てました。
よく見ていると釘が旨く打てない子供は金槌ではなくショックハンマーを使用していました。説明をして取り替えました。曲がって打ってしまい抜く
事が出来ず私たちの所へ持ってきたのでバールで抜いてあげました。4年生にはまだバールの使い方が良く解らないようです。
木箱へ8種類の水生植物植え付け
 出来上がった木箱に浮き上がらないように下に砕石を少し入れ、
その上に砂と土を混ぜた植え付け用の用土を口切に入れ、1種類づつ、一枡に5株づつ植えつけるように割り箸を使い穴をあけました。その中に
セキショウモ、クロモ、コウガイモ、リュウノヒゲモ、ヒロハノエビモ、ササバモ、この6種類は筑波大学より分けて頂き増やした物、ほかの2種類は
60年前まで涸沼に大量に繁茂していたマツモとヤナギモを植えつけました。
出来上がった木箱に浮き上がらないように下に砕石を少し入れ、
その上に砂と土を混ぜた植え付け用の用土を口切に入れ、1種類づつ、一枡に5株づつ植えつけるように割り箸を使い穴をあけました。その中に
セキショウモ、クロモ、コウガイモ、リュウノヒゲモ、ヒロハノエビモ、ササバモ、この6種類は筑波大学より分けて頂き増やした物、ほかの2種類は
60年前まで涸沼に大量に繁茂していたマツモとヤナギモを植えつけました。
マツモとヤナギモは昨年偶然に自然公園や地元の水田排水路に
出ていたのを見つけました。東日本大震災で地盤が30cmほど低下したのが影響しているのではないかと想像しています。ヤナギモについては
3mほどの広さにあるので、いつ無くなるか分からないので行政側に保存池の整備を請願している所です。